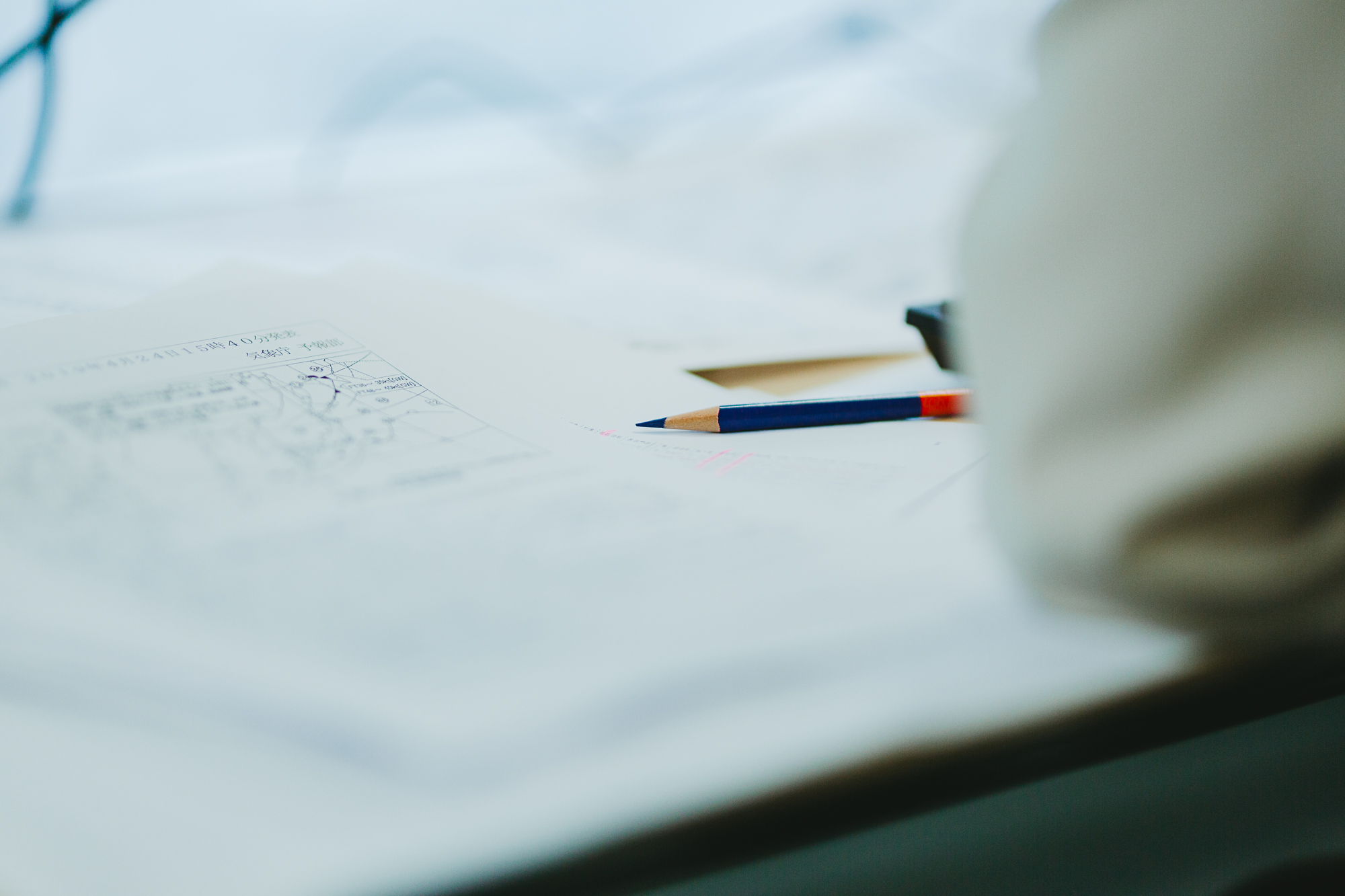沿革

| 1950年4月 | 運輸大臣から、財団法人気象協会の設立の許可を受ける |
| 1950年5月 | 財団法人気象協会設立 |
| 1955年5月 | 気象業務法による「解説予報業務」の許可を受ける(許可第5号) |
| 1955年7月 | 177業務を開始(仙台より順次開始) |
| 1966年4月 | 財団法人日本気象協会として全国統合 全国中枢機関として中央本部を設立 北海道・東北・東京・関西・福岡の5地方本部を構成 |
| 1973年2月 | 高速自動車道に対する独自予報業務を開始 |
| 1977年3月 | 気象情報センター(MICOSセンター)を設立 |
| 1977年12月 | 日本初の気象情報オンライン提供(MICOS)を開始 |
| 1983年10月 | 運輸大臣から情報化貢献企業として表彰を受ける |
| 1985年4月 | 中央本部に東京本部を統合 |
| 1990年9月 | 防災分野における国際協力及び災害対策に貢献した功績により内閣総理大臣から表彰を受ける |
| 1995年5月 | 気象予報士制度による局地的な予報サービスを開始 |
| 1996年12月 | 中央本部を東京都豊島区に移転 |
| 1998年2月 | 首都圏本部を設立 |
| 1998年6月 | 建設コンサルタント登録(道路部門) |
| 2000年1月 | ISO9001認証取得(首都圏本部)、2002年(北海道支社)、2004年(関西支社) |
| 2000年6月 | 本社・支社制とする 本社:企画本部、管理本部、営業本部、開発本部、国際事業本部、MICOS本部 支社:北海道支社、首都圏支社、東海支社、関西支社、九州支社 支局:東北支局 |
| 2001年9月 | 建設コンサルタント登録(建設環境部門)(河川、砂防及び海岸・海洋部門) |
| 2002年4月 | 建設コンサルタント登録(農業土木部門) |
| 2005年4月 | 本社本部を経営企画本部、管理本部、営業統括本部、技術本部の4本部とする |
| 2006年7月 | 建設コンサルタント登録(港湾及び空港部門) |
| 2007年1月 | 日本気象協会独自の桜開花予想スタート |
| 2007年2月 | ISO認証拡大(首都圏支社)登録活動範囲に気象情報サービスを追加 |
| 2007年12月 | 太陽光発電向け日射量予測(特許第5047245号、特許第5059073号)の運用開始 |
| 2008年6月 | WBGT熱中症予防情報の提供開始 |
| 2008年12月 | GPS可降水量等のリアルタイム情報を計算過程にデータ同化させた総合数値予報システム「SYNFOS-3D」を開発し(特許第5203104号)、実運用を開始 |
| 2009年2月 | ISO認証拡大(首都圏支社)、東北支局、中部支社、富山事業所を追加 |
| 2009年6月 | 『携帯型熱中症計』発売開始 |
| 2009年7月 | 本社営業統括本部と首都圏支社を統合し、事業本部を設け事業部制とする |
| 2009年9月 | Twitterユーザーによる「tenki.jp」のフォロー数が10万人を突破 |
| 2009年9月 | 内閣総理大臣から一般財団法人への移行認可を受ける |
| 2009年10月 | 一般財団法人日本気象協会となる |
| 2010年1月 | 事業本部、支社、支局においてISO9001の認証を統合 |
| 2010年7月 | 「H21利根川上流域温暖化モニタリング検討業務」において、国土交通省関東地方整備局より、優良業務及び優秀技術者表彰を受ける |
| 2010年7月 | 「波浪うちあげ高予測システムに関する調査業務」において、国土交通省国土技術政策総合研究所より、優良業務表彰を受ける |
| 2010年7月 | 「降雨予測システム改良その他業務」において、国土交通省近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所より、優良業務表彰を受ける |
| 2011年3月 | 「複数の津波高さに対応した津波ハザードマップ整備に関する検討業務」(内閣府)により複数の津波高さに対応した浸水予測図を作成 |
| 2011年4月 | 山手線などのトレインチャンネルに天気予報を提供開始 |
| 2011年7月 | 「降雨予測システム改良その他業務」において、国土交通省近畿地方整備局より、優良業務及び優秀技術者表彰を受ける |
| 2011年11月 | 建設コンサルタント登録(廃棄物部門) |
| 2012年7月 | 「XバンドMPレーダの雨量観測精度等の算出業務」において、国土交通省国土技術政策総合研究所より、優秀技術者表彰を受ける |
| 2012年7月 | 「日東道地吹雪等視程障害対策検討業務」において、国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所より、優良業務表彰を受ける |
| 2012年9月 | 民間気象会社初のXバンドMPレーダの導入 |
| 2012年12月 | ISO27001認証取得(システム管理部、環境事業部、情報システム事業部) |
| 2013年3月 | 風力発電事業の環境コンサルティングに特化した「環境影響評価室」を新設 |
| 2013年4月 | 日本気象協会メセナ企画にて「季節のことば36選」を選定し発表 |
| 2013年5月 | 「平成22年・23年度新潟支社管内気象予測業務」において、東日本高速道路株式会社新潟支社より、優良業務表彰をうける |
| 2013年7月 | 空にかざして豪雨を探知する『Go雨!探知機 -XバンドMPレーダ-』(特願2013-090981)の提供を開始 |
| 2013年10月 | 京都大学防災研究所に寄附研究部門として気象水文リスク情報(日本気象協会)研究分野を設置 |
| 2013年12月 | ユーキャン流行語大賞にて「PM2.5」がベストテンに選出され受賞 |
| 2014年7月 | 本社の4本部を管理本部と事業本部の2本部に再編し、事業本部を事業統括部、防災ソリューション事業部、環境・エネルギー事業部、メディア・コンシューマ事業部、情報サービス部の5部とする |
| 2016年5月 | ひまわり8号のデータを活用した、高解像度・高頻度の衛星推定日射量を配信するサービスを開始 |
| 2017年1月 | 平成28年度 省エネ大賞で「経済産業大臣賞(ビジネスモデル分野)」を受賞 「需要予測の精度向上・共有化による省エネ物流プロジェクト」にて |
| 2017年4月 | 商品需要予測事業に特化した「先進事業課」を新設し事業開始 |
| 2018年7月 | 最高情報責任者ならびに最高技術責任者を新設 |
| 2020年5月 | 創立70周年を迎える |
| 2020年6月 | 物流向け新サービス 「GoStopマネジメントシステム」提供開始 |
| 2021年1月 | 「余剰電力予測サービス」が 令和2年度「新エネ大賞」新エネルギー財団会長賞を受賞 |
| 2021年6月 | 顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術を開発 |
| 2021年9月 | 「GoStopマネジメントシステム」が 「2021年度ロジスティクス大賞」を受賞 |
| 2022年1月 | 人流・気象データなどを活用した小売り・飲食業界向けAI需要予測サービス「サキミル」を提供開始 |
| 2022年4月 | 日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトにて、「暑熱順化前線」を公開 |
| 2022年11月 | 気象で社会と生活の質を向上し持続可能な社会の実現を目指した 「ウェザーマーケティングプロジェクト」始動 |
| 2023年2月 | 『JWA統合気象予測』を開発し、高精度・高頻度・高解像度の気象予測を提供 |
| 2023年3月 | 気象データで社会と生活の質を向上し、持続可能な社会実現を目指すウェザーマーケティング情報メディア「Weather X」公開 |
| 2024年3月 | 物流効率化の推進のため 経済産業省委託事業にて実証実験を実施 需要予測情報を共有した複数事業者協働により工場・店舗のパフォーマンス向上を達成 |
| 2024年4月 | 「線状降水帯の検出技術の開発」にて令和6年度 文部科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞 |
| 2024年4月 | ビジネス向け天気予報アプリ「biz tenki」提供開始 |
| 2024年6月 | 気象業界初となる「2年先長期気象予測」を提供開始 |
| 2025年3月 | 『「2年先長期気象予測」で実現する電力需給の最適化と脱炭素社会』の取り組みが「2024年度NIKKEI脱炭素アワード」にて大賞を受賞 |
| 2025年4月 | 令和7年度 文部科学大臣表彰(科学技術振興部門)を受賞 「季節予報の基盤技術の開発に基づく社会実装の振興」 |
| 2025年5月 | 創立75周年を迎える |